| Mariamma's Homepage(インド、南アジア総合情報) |
マリアンマのHP
What's New
月刊『インド通信』
| 『インド通信』(インド、南アジア情報月刊誌) |
インド通信のHPと最新号情報
バックナンバーとホームページエッセイ
インド通信の催し物ガイド
インド通信の新刊情報(最新版)
新刊情報(バックナンバー)
インド通信バックナンバー
2000.11.1発行、第265号
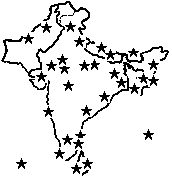 <シリコンバレーのマサーラー・シアター>
<シリコンバレーのマサーラー・シアター>先月の「湾岸諸国のインド人報告」に続いて、今月はアメリカのインド人とインド映画について。本誌の誌面の方には、シャールク・カーンらボリウッド映画スターが出演して、ひと夏かけて英米各地を巡業した「WANTED LIVE」のロサンジェルス公演の鑑賞記も掲載されています。
今年行われた国勢調査で、アメリカのインド人は120万とも150万になるとも言われている。実数は留学や短期就労で来ているのを含めてもっといるだろう。それがシャールク・ショー全米興行の観客だ。そのまた多くがエンジニアとして、言わずと知れたカリフォルニアのシリコンバレーで世界のIT産業を支えている。
バレーの中心サンノゼの隣り、フリーモント(バレーのベッドタウンでインド人が多い)にパキスタン人実業家がインド娯楽映画専門映画館NAZ(ナーズ)を作ったのは90年代の始め。廃業した小さな映画館を転用したものだった。同じ頃、全米の大都市にインド映画館がいくつも登場し、アメリカはインド映画の一大市場に成長した。
ナーズは昨年ディワーリー祭の日、同じフリーモントの大ショッピングセンターの一画に、8つのスクリーンを持つ大劇場、ナーズ8をオープンした。一度に8つの映画を上映する、または人気作は一度に複数のスクリーンで上映するというシステム。アジア映画館として中国、韓国映画の上映も謳っていたが、最近はほとんどインド映画、しかも大半がボリウッド作品になってしまった。ここらに南インド人は非常に多いが、タミル、テルグ映画はそれほど流行らないとかで、印米合作の「ジーンズ」もあまり知られていない。
ナーズ8では入場券は映画を指定して買うが、席に空きがあれば館内で移動してどのスクリーンを見てもよいので、一日かけて何本も見ることができる。チャートをむさぼり、家族やデートの一行と並んで映画に耽溺するのは、生き馬の目を抜くバレーにあって至福の瞬間なんである。
<そして、NYでシャールクを見る>
マンハッタンのペンシルヴェニア駅から、野茂、吉井も投げたメッツのシェィ・スタジアムに向かう地下鉄で、ニューヨークきってのインド街と聞こえたジャクソンハイツに行った。地上にある駅の階段から見まわすと、何と駅はインド街の只中。十字路を中心に四方にそれぞれ1、2ブロックほどの通りが、南アジア系の商店〜サリー、雑貨、音楽など、で埋まっている。
遠からぬ所に人だかりが出来ていた。何だと聞くと「そこの店にインドのスターが来ている」と言う。あたりから浮いたような美麗な宝飾店、店頭に貼られた広告ポスターを見て息を止める。店先には黒塗りの、ハリウッド・スター御用達のごときリムジンが。「もしかしてシャールクか?」と尋ねると、群集はこっちの顔を覗き込んで「何でシャールクを知っているんだ。あんたネパール人か?」地元の有力者(Wanted Liveのスポンサーなど)のための「限定ファンの集い」が店内で行われているという。シャールクは店の商品である高級時計の宣伝キャラクターなのだ。
話し掛けてくれたのは、子供ターバンもかわいい少年を連れたシク教徒のご婦人方("Kuch Kuch Hota Hai"の坊やみたいですね、とお世辞も忘れない)。シャールクの登場を期待して、皆といっしょに待つことにした。あたりにはバングラデシュの女性の一団、さらにパキスタン人の商店主に南インドの青年グループ等々。ここのインド街の店や客層はグジャラーティーとかパンジャービーとか特定のグループが多いということなく、南アジア各地がまんべんなく混ざっているのが特徴らしい。会話のノリといい真っ昼間にぼけらーっと待っているのといい、極めて南アジアな情景だが、グラサン黒スーツのマッチョなボディー・ガードとNYPDのロゴ入りの青いジャケットのNY市警のおねえさん方が時々「道にはみださないで〜」と交通整理するのがアメリカであった。
なぜか地元インド系テレビ局のカメラを向けられインタビューされたりして待つこと約30分、突然群集が店の後方に走り出した。人垣を分けるように黒いリムジンがゆっくり向かってくる(店の正面のリモはダミーだった!)私たちの前を歩くほどの速さで通った瞬間、リモのルーフトップが開いてシャールクが半身を出した。黒タキシードに蝶ネクタイで、愛敬ふりまいて手を振る。おいおい、これってまるで映画じゃん!
この間おそらく数秒。それでも手の届くような距離でシャールクの顔ははっきり見えた。色が浅黒く、映画で見るのと同じ顔をしていた。皆一緒にリモを追っかけ、おばさんもアメリカ生まれのインド・ギャルもキャーキャーと叫んで、去り行くシャールクに手を振り返した。
この夏、アミターブの息子のアビシェークは全米のインド映画館やインド系寺院などをまわっていたそうで、アミターブの映画で育ったシリコンバレーの働き盛りのエンジニアたちは、その姿に父親の再来かと感涙の涙を流したとか。大学の留学生にスターの子弟がいて、子供を訪ねてきたスターに会えたという話もあった。ヴァンクーバーのホテルで、ロケに来ていたリティーク・ローシャンにばったり出くわした友人は思わず「ハイ!リティーク」と声をかけたら「ハーイ」と手を振ってくれたそうである。夏の北米は本物のインド・スターに会える、実に穴場であるらしい。
目次
・南アジア地誌事典・第57回「インダス文明都市カーリーバンガンにて」(野口 浩史)
# 右上地図の星印「南アジア地誌事典」にこれまで登場した主要な土地
・インドの植物「トウ」(西岡 直樹)
・ガラムニュースSpecial「夏の北米、インド映画三昧??」(本HPの冒頭エッセイに一部紹介)

