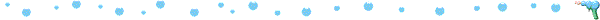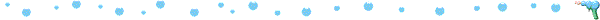
文学、言語はまったく専門外ですが、一読者としてここ数年ハマっています。インド研究の上では主流と離れていますし、ほとんど日本に紹介されることがない作品ばかりですが、かえって新鮮な思いで読むことが出来ます。実は英米文学の中では最近注目されている分野でもあるのです。
メール等でいろいろなお問い合わせをいただくようになりました。新しい作品を読んでいるのですが、なかなか書評として書く余裕がありません。邦訳の新刊については、随時「インド通信のホームページ・新着情報」で紹介していますので、ご覧ください。
このHPでは少し前に書いた文献を、本文のまま掲載していますが、それ以外にも関口真理の名義で、以下のような執筆物があります。新しいものは当面HPには掲載できませんので、以下の誌面をご覧ください。ホームページにその内容が紹介してあるものにはリンクが張ってありますので、どうぞご覧ください。リストに続いて、インド人の英語文学について簡単に解説します。
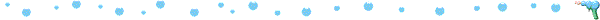
2001/02年 「連載:アジア文学散歩 インド、南アジア系作家の英語文学」 ・月間ニュースレターの小エッセイコーナー。注目の作家と作品紹介。2001年 「海外文学はいま:インド 歴史と伝統に立つ若い文学」
・月間ニュースレターの小エッセイコーナー。注目の作家と作品紹介。2001年 「海外文学はいま:インド 歴史と伝統に立つ若い文学」
・『アジアクラブ・マンスリー』 2001年10月号より2002年7月号まで連載。(財)アジアクラブ発行 ・インド系英語文学の発生から現在までの流れを、インド国内と欧米で概観した。邦訳のあるインド英語文学作品の一覧も掲載。1999年 「A.B.C.D. -アメリカのインド系移民の子供たち-」
・インド系英語文学の発生から現在までの流れを、インド国内と欧米で概観した。邦訳のあるインド英語文学作品の一覧も掲載。1999年 「A.B.C.D. -アメリカのインド系移民の子供たち-」
・『民主文学』2001年3月号掲載。民主主義文学同盟発行。
 ・若い移民と、移民二世の暮らしぶり。素材としてインド系少女が主人公の児童文学、若い移民二世のアイデンティティをテーマにした小説を紹介した。1999年 関口真理、小磯千尋編著 『ワールドカルチャーガイド9:インド』1999年、トラベルジャーナル発行。
・若い移民と、移民二世の暮らしぶり。素材としてインド系少女が主人公の児童文学、若い移民二世のアイデンティティをテーマにした小説を紹介した。1999年 関口真理、小磯千尋編著 『ワールドカルチャーガイド9:インド』1999年、トラベルジャーナル発行。
・『コッラニ』15号所収、コッラニ編集部<問>03-3773-0960 臼田
(コッラニはインド、南アジア専門の文化、文芸、研究エッセイ誌。ほぼ年一回刊行) 「インド人作家の”英文学”が面白い」1999年 "Between ABCD and DCBA: Rise of the New Generation in Asian Indians in the United states"(English paper in PDF format), International Symposium ' South Asian Migration inComparative Perspective - Movement, Settlement and Diaspora -' The Japan Center for Area Studies 国立民族学博物館地域研究企画センター特別共同研究「人口移動の比較研究」 第5回国際シンポジウム「南アジアの人口移動の比較研究 移動・定住・ディアスポラ」における研究報告。2000年夏、報告書刊行予定。
「インド人作家の”英文学”が面白い」1999年 "Between ABCD and DCBA: Rise of the New Generation in Asian Indians in the United states"(English paper in PDF format), International Symposium ' South Asian Migration inComparative Perspective - Movement, Settlement and Diaspora -' The Japan Center for Area Studies 国立民族学博物館地域研究企画センター特別共同研究「人口移動の比較研究」 第5回国際シンポジウム「南アジアの人口移動の比較研究 移動・定住・ディアスポラ」における研究報告。2000年夏、報告書刊行予定。
「ヌーベル・インド英語文学の話題作」
「美貌の作家、ショーバー・デー」
インド英語文学の概略、注目作のリスト
1998年 アルンダティ・ロイ、工藤訳『小さきものたちの神』DHC(インド作家による英国ブッカー賞受賞作の翻訳に対し、インド関連事項の解説、監修)
1998年 「ロイの作品に映し出される現代インドの息遣い」、『イングリッシュ・ジャーナル11月号』アルク(歴史、社会的背景から見た『小さきものたちの神』作品論)
1996年 「恐怖の大女神」、『本の話10月号』文芸春秋社(翻訳されたインドの文学作品の背景として現代史を読む作品論)
1992年 「海外のインド系作家たち」、『インド通信161号』、1992年2月、インド文化交流センター(英米の文壇で執筆する作家と作品の紹介)
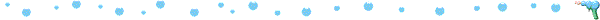
ピューリッツアー賞といえば報道部門が有名だが、ほかにも芸術、文芸の諸部門があり(こちらもアメリカではそれなりに権威があるらしい)、先ごろ2000年度の受賞者が発表された。この文芸フィクション部門を受賞したのが、1967年生まれのインド人移民二世の女性作家ジュンパー・ラヒリー。対象となった短編集"Interpreter of Maladies"は、デビュー作で、表題作ではインドに「里帰り」したアメリカの移民二世夫婦が、観光に出かけたオリッサのコナーラク寺院でひとりのタクシー運転手に出会う。運転手自身はオリッサではなく異郷のグジャラート出身で、病院でオリッサ人の医師にこの地域では少なくないグジャラーティーの患者の通訳をするというもう一つの仕事を持つ。二重に異文化の接触を描き、居場所探しをしている人々の姿を浮き彫りにする。そのほかの収録作品もすべてインドか、アメリカのインド移民を題材にしている。
ちなみに毎年アメリカですぐれた短編小説を選んでまとめられる「ベスト・アメリカン・ショート・ストーリーズ1999」にはラヒリーの表題作と、やはりアメリカで活躍するインド人女性作家チットラ・ディヴァカルニーの作品が収録されている。ディヴァカルニーの長編小説「シスター・オブ・マイ・ハート」(「ワールドカルチャーガイド:インド」でも紹介)と、「ショート・ストーリーズ1999」は年内に邦訳が出版予定とのことである。
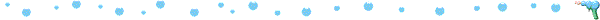
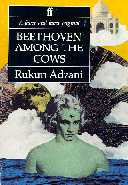
インドにおいて、英語は植民地時代の支配者の言葉であったわけだが、イギリスが持ち込んだ「近代的教育」の言語として、高等教育を受けた人たちの共通語になった。独立後も、全土に存在するあまたの言語の中から絶対優勢な「国語」を選び出すことができず、多くの「公用語」を認め続ける現状の中で、英語は行政、ビジネス、教育の分野などで、全国に通用するという優位さを失ってはいない。
しかしインドの文化、言語を尊重する立場から、英語は限られた階層の言語という否定的な捉えられ方をすることが多い。学生の頃に聞いたあるインド文学に関する講演では「英語文学ははインドの文学ではない」と断定していた。実際ベンガル語やタミル語の文学は千年単位の歴史と伝統を持っている。そうした話にはついうなずいてしまうので、ナーラーヤンの作品でも読んでみようか、という気になる人はあまり多くはない。
*インドの公用語:憲法に定められた公用語はデーヴァナーガリー文字表記のヒンディー語ひとつだけ。しかしヒンディー語の優先に対しては、元々ヒンディー語を使用してこなかった人々、特に南インドからの反発が強かった。そこで国の公用語の他に、憲法の付則条項で、各地域で優勢な言語を中心に使用の促進が望まれる言語として現在18言語が指定されている。付則言語は州レベルで公用語とされたり、初等教育の言語となっている。一般に概説書などではこれらも公用語と紹介されている。
ところが、実際インドの本屋に行ってみると英語の本が溢れている。こうした本屋のベストセラーリストに並んでいるのは、シドニー・シェルダンとかスティーヴン・キングなど世界的な売れ筋なのだが、インド人が書いた本の点数も確実に増えている。
同年代の友人は文学少女あがりで、当然大変な読書家で、自分も詩やエッセイを書く仕事をしている。彼女は「私たちは話し言葉はヒンディー語だけど、読み物は初めから英語だった。だから文学の手法は、英語で書く方法しか知らない」と言う。特に幼稚園から学校の言葉は英語、で育っている都市部の若い世代にはこうした傾向が強くなっている。こうなっては英語文学はインドの文学ではない,などとは言えなくなってきた。先のエッセイを書いた92年当時は、インド系作家といえば、ラシュディのような在外インド人で、主に欧米の読者を対象に描いていたが、今はインドに住むインド人作家が書いた作品も数多く英語文学のマーケットに通用するようになり、一方でインド国内の読者層も市場も拡大してきている。その象徴的な出来事が、アルンダティ・ロイの1997年英国ブッカー賞を受賞である。彼女はインド在住のインド人としては初めての受賞者となった(これまで在外インド人作家の受賞はある)。
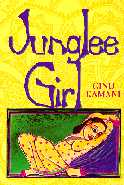
*アルンダティ・ロイ「小さきものたちの神」Arundhati Roy,"The God of Small Things"
新人の作品に対する史上最高額の契約金だったとかで、出版前からとにかく話題になっていた。英米を中心にベストセラーとなり、諸言語に翻訳された(日本語版は工藤惺文訳で1998年、DHC刊)。作者の母、メアリー・ロイはケララの教育者、社会運動家。本人は建築家から女優、脚本家と転身し、そのユニークなファッションやライフスタイルも話題になっている30代半ばの女性。彼女の処女小説であるこの作品には自身の体験が多分に反映されていると思われる。
舞台の中心は1969年、独立後インドを代表する政治家、ナンブーディーリパッドゥー(98年死去)が率いる共産党州政権時代、ケララ州コッタヤム郊外のアエメネムという川沿いの村。母親はこの地で有力な高位カーストのシリア・クリスチャンの旧家出身、父親はベンガル人のヒンドゥー教徒という7才の男女の双子エスタッパン(アラヴィンダン監督の映画を思い出す名前)とラヘルは、両親の離婚によって母アムーとともにアエメネムにやって来る。アムーは家族の反対を押し切って結婚し、しかも出戻り。双子の父は異教徒。ということで、プライドが高く旧世代の価値観を持つ双子の祖父母や大叔母、イギリス留学帰りの叔父、果ては使用人にまで冷ややかに迎えられることになる。それでもバックウオーターやヤシ畑に囲まれた美しい南国の自然の中で子供たちの日々は一瞬輝くが、叔父の別れた英国人の妻と娘が休暇を過ごしにアエメネムを訪れたのをきっかけに、旧家の歴史の崩壊が始まる。悲劇的な結末も子供の目を通して描かれることによって、清浄観の漂う余韻が残る。また、アムーと被差別カーストの青年との恋、旧家を取り巻く村や周囲の人々、地方の政治、新旧世代の対立といったインドの様々な現実がエピソードとして、巧みに物語に織り込まれている。小説ファン以外にも一読の価値あり。
E.M.S.ナンブーディリーパッドは作中、実名で描かれているが、共産主義者を標榜しながらケララの伝統社会を引きずるEMSとそのシンパたちが揶揄されている部分が何ヶ所かある。これに対して雑誌論説などでEMSは正面切って反論した(はからずもEMS最晩年の厄介事となった)。また、異カースト間恋愛を描いたことに関しても反発を買い、反対者は「公序良俗に反する表現」として裁判に訴えた。作品発売後のこうした余波がさらに話題となり、現在もインド国内のベストセラーとなっている。