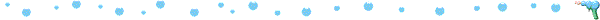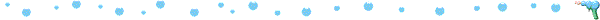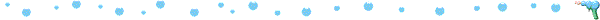インド人・インド系作家の英語文学
小さきものたちの神
The God of Small Things
by Arundhati Roy
(翻訳:DHC \2,300)
関口 真理
Last Revised: March 18, 2000
「小さきものたちの神」を知ったのは原著の発売よりも以前、フラミンゴ社がアルンダティ・ロイに新人としては破格の契約金を出したということがインドのマスコミで報じられた時だった。実は数年前、インドの文学界には似たような話があった。詩人として既に知られていた若手作家のヴィクラム・セト Vikram Seth初の長編小説「良縁 A Suitable Boy」が高額の契約金でイギリスの出版社に認められた例である。「良縁」は欧米でベストセラーとなりブッカー賞も当然視されたが、実際はノミネートすらされなかった。これに苦い思いを抱いていたインドの文学界は、ロイのブッカー受賞でやっと溜飲を下げることができた。さらにはインド初の快挙として大いに話題になり、普段は本を読まないような向きも本屋に走ったということである(本インタビュー中にも語られている)。
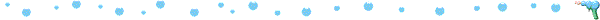
作者アルンダティ・ロイはインドの最南端ケララ州の地主で、ピクルス工場を経営する旧家のお嬢さんでありながら、幼少時からのアウトローな性質で勘当同然の身となった。「他に行く所がなかったから」建築学校に学び、イタリア留学を果たすもこの仕事を続ける気が起きず帰国。やがてデリーで知り合った男性と結婚、二人の娘が生まれる。この夫がたまたま映画監督だったという縁で脚本家や批評家、女優まで経験した。そんな仕事をこなしながら数年かけて書いたという処女小説が「小さきものたちの神」である。このプロフィールを意識して作品を読めば、本作にはロイの体験が各所に色濃く投影されているという指摘はうなずける。
多彩な人生経験を持つ、まだ三十代の女性---グラビアに登場するロイはカールした髪を無造作に束ね、ある時はくたびれたTシャツにジーンズ、ある時はエスニックなキルトをつぎはいだブルゾンと、およそ高尚な文化人とは縁遠い外見をしている。それが作品の大胆な中味と合間って、眉をひそめる向きもある一方、経済成長で激変する都市の若い中間層には彼女自身の言動やライフスタイルが話題になっている。最近では印パ核実験に反対して、インド国内としては強硬な論陣を張って注目された。
「小さきものたちの神」は、男女の双子の目に映ったケララのある旧家の没落の歴史である。物語は打ち捨てられた屋敷に成人した主人公ラヘルが帰ってくる現在と、一家に悲劇が押し寄せた1969年の間を行き来しながら進行する。幼い双子のエスタとラヘルは離婚した母と共にケララの村でピクルス工場を経営する母の実家に引き取られる。実家は世間からの尊敬を受けるシリア・クリスチャン(使徒トマスが伝道したとされる古い宗派。ケララでは社会的にも優勢)の家柄であったが、イギリス統治時代の栄光に浸り、英国崇拝者である祖父と叔父が、インドの伝統的な女性蔑視の価値観で祖母や大叔母を支配していた。その大叔母たちの鬱積した思いは、出戻りである母や、父親がクリスチャンではない双子を一族の恥、厄介者として非難することに向けられる。
一方、家の外である村は川と水路に沿い、魚が踊り、赤いラテライトの大地を緑濃い熱帯の木々や花々が覆う、色彩の鮮やかな美しい土地である。しかしケララと村の社会は変わりつつあった。1957年、作中にも実名で登場するE.M.S.ナンブーディリーパッドの率いるインド共産党が世界で初めて選挙による共産党州政権を樹立(インドでは各州に首相、内閣、議会があり独自の施政が行われている)、物語の69年はその2度目の政権の時期にあたる。工場の労働者や村の活動家の動向に、旧家の威厳だけでは対抗できない時代になっていた。一方でケララはインドの中でもカースト差別の激しい地域とされてきた。特に不可蝕民と呼ばれる人々は私たちが知っているカーストの四ランク以下の存在で、ほとんど人間とは扱われていない。作中でもあたりが汚れるからと言って、箒で足跡を消して歩く、という描写が出てくる。こうした差別を支えていたのは、伝統的なヒンドゥー教の価値観と高位のカースト、地主といった旧来の勢力であるが、実はE.M.S.自身、また多くの共産党指導者、支持者が高位カーストの出身でもあった。共産党は社会改革を標榜しながら果たせず、やがて混迷に陥っていくのだが、そうした自己矛盾が村の共産党活動家ピライ同志(彼もまた有力カーストの出身)が不可蝕民ヴェルータを見捨てるくだりにも端的に表れている。シリア・クリスチャンも長い歴史を経てクリスチャン・カーストとして位置づけられ、インド的な価値観を身につけている。使用人であるヴェルータへの一家の振る舞いを見れば分かるだろう。こうして内と外から一家は追いつめられ最後の悲劇へと突き進んでいく。
この物語は様々な点でケララという一地方の小さなコミュニティーの特色を際立たせながら、現代インド社会が独立から50年経った今日も抱え続けている普遍的な問題を提起している。世代間の対立、イギリスとインド、地方の政治、宗教、カースト、コミュニティー、ジェンダー、こうした要素が複雑に絡み合い、矛盾が生じる。一方でその摩擦が社会を動かす力にもなっていく。悲惨な結末にも関わらず絶望感がないのは、そうしたインドの生気がどこかに感じられるためかもしれない。本書は優れた英文学の読み物という当然の評価だけでなく、インドの社会、現代史のサブテキストとしての価値も併せ持っているのである。
『English Journal』 (アルク刊)1998年11月号掲載。
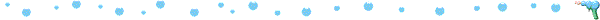
関口のホームページに戻る