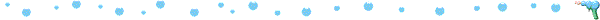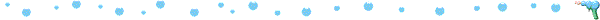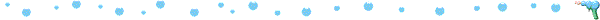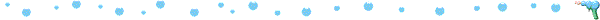インド人・インド系作家の英語文学
海外文学はいま:インド 歴史と伝統に立つ若い文学
関口 真理
Last Revised: July 1, 2002
初出:『民主文学』2001年3月号掲載。民主主義文学同盟発行。
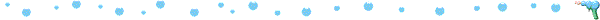
世紀の変わり目の今、インドが世界に誇る輸出品が三つある。ミス・コン美女、IT技術者と英語文学だ。
1994年に2人のインド女性がミス・ユニバースとミス・ワールドの栄冠に輝いて以来、毎年のようにどこかの世界美女コンテストでインド代表が優勝している。ただでさえゴージャスな彼女たちだが、映画女優になったり、スーパーモデルになったり、メジャーリーグ選手の恋人になったりとさらに注目を集め、インド女性はたおおやかで慎ましいというイメージは打ち破られた。
少し前はハイテク、今ではITと言った方が聞こえがいいのかもしれない。コンピューターの2000年問題を解決し、シリコンバレーの有数の企業はもはやインド人技術者なしでは機能しないといわれる。彼らの活躍は実際はだいぶ以前からのことだが、ことさら世界が騒ぐようになったのは90年代半ばからだろう。インドにとっては「頭脳流失」というあまりありがたくない事実だったのだが、今は世界と提携してインドもIT立国を誇るようになった。
そしてインド人の書く小説が次々欧米の著名な文学賞を取り、ベストセラーリストに並んでいる。英文学の文壇もインド人なしでは成り行かないと、これまたどこかの評論家が言っているらしい。
一連の事項は相関関係にある。インドは経済危機をきっかけにした1991年に歴史的な経済政策の転換を行って、外資の導入や規制緩和を断行した。その後インドは経済ブームに湧き、新たなビジネスチャンスをものにしたミドルクラスが台頭し消費生活を謳歌するようになった。停滞の一時期を経て、今度はIT革命で人材を内外に向けて輩出し、国内でも関連産業が大躍進しさらに経済発展は加速している。
多チャンネル化したテレビ、広告満載のグラビア雑誌が次々と創刊され、モデルやタレントの活躍の場が爆発的に増えた。ミスコン美女に触発された少女たちの将来の目標として、モデルや芸能人はそれほど遠いものではなくなった。アメリカナイズされた都市の生活、そして生活のかなりの部分を英語で暮らす人々は、自分たちの目線、自分たちの言葉で書かれた文学を受け容れた。それが新しいインド英語文学なのである。
インドの多言語状況と英語の役割
広大なインドには、地域によって有力な多数の言語が存在する。インド憲法によって国家の公用語とされるヒンディー語のほかに、17の言語がヒンディー語に準じる公用語として認定され、地域(州)の共通語として通用している。逆に言えば、日本の日本語、中国の中国語のように、国中どこでも通じる絶対的な言葉がない。ヒンディー語の話し手は最も多いが、まったくヒンディー語のわからないインド人も相当数いる。なにしろ人口が10億人を超える国であるから、ヒンディー語に次ぐ話し手を持ついくつかの言語でも、ゆうに数千万から1億以上の大勢力である。インド東部とバングラデシュで使われるベンガル語人口は、2億人を超える。人口だけならば、世界有数の大言語がいくつもインドに存在しているようなものである。
一方、英語は植民地時代を通じて、広くインド、南アジア地域の共通語的な存在になっていた。しかし支配者のもたらした言葉であり、それを使うのもイギリス人と接する機会のあるような限定されたインド人であるという、いわば階層限定的な負のイメージがつきまとった。インド独立の時点ではヒンディー語を全国に行き渡らせ、英語に代わる共通語にすることを目指したものの、歴史と伝統を自負する各地の有力言語からの抵抗にあって、多くの言語が並立した状態の解消は進まないままである。そのため共通語としての英語の重要性は現在も変わることがない。
国会や行政など公式にヒンディー語と英語が使用されているほか、全国から学生が集まる大学などの高等教育機関では、ほとんどの講義が英語で行われている。近代の教育、文化のシステムがイギリスによってもたらされたことから、高等教育をわざわざインドの言語に置き換える必要もなかったのである。もちろん、一般企業やインド各地から人材が集うような組織でも英語が共通語である。
そんな事情だから、都市部を中心に子供の将来を教育に託す親たちは、幼稚園や初等学校レベルから英語教育の学校に送る。国土が広大なインドでは、地方出身や親が転勤を繰り返す子供が全寮制の学校に行くことも珍しくない。こうしてあるレベル以上の教育を受けた子供たちは、幼いころから少なくとも学校や友達どうしでは英語で生活するのが当たり前になるのだ。しかも親も同じような経歴だったり、両親が異なる言語圏の出身だったりすると家庭内でも英語生活になる。そして海外での活躍のチャンスも増えた今、英語教育への需要はさらに高まっている。
このような環境で育った人たちは、話すには身近なインドの言葉を身につけるものの、読み書きはごく幼い時から英語である。学校や家庭にある絵本や読み物の多くも、欧米の英語の作品だ。私たちが国語の時間に名作の断片を読み、夏目漱石を教養として知り、流行作家として村上春樹を読むように、彼らはギリシア叙事詩からシェークスピア、ジェーン・オースティンを自国の文学より詳しく学び、スティーヴン・キングの新作に飛びつく。小説や詩、散文エッセイといった文学の形をしたものは初めから英語でしか知らないという人も少なくない。
現在のようにインド自前の出版物が多くはなかった時代にも、どこかから入手した欧米のティーンエイジャー雑誌が、クラスの中でボロボロになるまで廻し読みされていたとか、ラジオの数少ない欧米ポップ・ロック番組をむさぼり聞いていた、という逸話をよく耳にする。経済開放以前からアメリカナイズされた知識と文化は若い層に確実に浸透していた。そうした人々にインドの言語の文学は、リズムも乗りも異質な存在と映り、むしろ欧米の文学に手を伸ばしてしまうのは仕方のないなりゆきだった。
そして90年代の幕開けとともに、インド人の手になる小説が次々登場してきた。英語とポップカルチャーで育った世代が自分の言葉で書き始めたのだ。そしてそれを受け入れる読み手の市場もまた成熟していたのである。
インド英語文学の流れ
インドの英語文学もインドの英語同様、複雑な立場にあるが、その定義はあまり厳密ではない。筆者は文学が専門ではないので、そうした分析は他項に譲るが、本来インド人にとって外国語であるはずの英語で書かれているという、国民文学としてはいわば特異な存在である。
この分野の先駆けの作品は1930年代に遡る。まだ植民地下にあり、インドでインド人が本を刊行するのも難しかった時代であるが、変化する時代を象徴するような作品が書かれている。
今日も文壇の第一線にいるR.K.ナーラーヤンはインド英語文学の大御所ともいえる存在で、南インドの架空の町マルグディを舞台とした一連の作品で知られているほか、紀行や昔話の紹介でもインド文学界に寄与している。彼と同年代ではマハトマ・ガンディーの影響を強く受けたムクル・ラージ・アーナンド、歴史に題材を取った娯楽性の高い長編を書いたマールゴンカール、長いキャリアの中で時代に応じた多彩な題材を扱い、評論家的活躍もするクシュワント・シンらがいる。少し遅れて女性作家アニター・デサーイーが登場し、さりげない日常生活や心情を描き、女性や若い読者に人気を広げた。
また、インドにはアングロ・インディアンというユニークなマイノリティーがいる。彼らはイギリス人とインド人の混血、あるいは独立後もインドに居残ったイギリス人の子孫で、英語を母語としている。現実にはイギリス人でもインド人でもない微妙な存在だが、教育や文芸の分野で活躍してきた。文学におけるその代表はラスキン・ボンドで、在住するヒマラヤ山麓をテーマにした叙情的な作品や児童文学で定評がある。新しい作家では、自らの家族史を題材にした「トロッター・ナーマ」などを書いているアラン・シーリーがいる。
しかしインド英語文学の範疇はインドのインド人作家だけに納まらない。70年頃から移民してインド以外の土地に住む、インド系移民やその子孫が書く作品が欧米の文壇で知られるようになった。インドでは移民作家をインドの作家とは認めとようとしなかったが、世界の文壇では彼らをインド英語文学作家に含めるのが定着している。
トリニダード出身のV.S.ナイポールは一貫して批判的なインド文明論を展開する大物作家である。インド独立、パキスタンとの対立を題材にした「真夜中の子供たち」でブッカー賞を受賞し、「悪魔の詩」事件で世界を震撼させたサルマン・ラシュディーは、一族がインドとパキスタンに分断されたイスラム教徒の出身である。ラシュディーはその後も、イギリスのインド移民、インドの宗教対立などほとんどの作品で現代インド、南アジアをモチーフにしている。
最近では英米を中心にさらに若い世代の作家が、移民マイノリティーで生きる自分たちの現実を等身大で表現している。
イギリスでは、まずパキスタン系移民の青年を主人公にした映画「マイ・ビューティフル・ランドレッド」の脚本で注目され、「郊外のブッダ」などで小説家としての地位を確立したハニフ・クレイシー(自身はパキスタン・英国のハーフ)あげられる。続いて、やはり脚本と小説を手がけるインド系女性作家のミーラー・サンヤル(「アニターと私」、「人生はアハハ、ヒヒヒじゃない」)、パキスタン系のアユーブ・カーン=ディン(「ぼくの国、パパの国」)が活躍している。
アメリカでは英文学者でもあるバーラティ・ムーカジ(「ミドルマン」=全米書評家協会賞、「ジャスミン」ほか)や、チットラ・バネルジー・ディヴァカルニー(「お見合い結婚」、「シスター・オブ・マイ・ハート」など)がすでに高い評価を得ているほか、デビュー作「疾病の通訳(邦題・停電の夜に)」でピューリッツアー賞を受賞した移民二世のジュンパー・ラヒリーなど、新しい作家と作品が次々登場し、インド系作家は宝の山のような評価が出来ている。
カナダ在住のロヒントン・ミストリーはストーリー作りが巧みで、出身地のボンベイを舞台にした「かくも長き旅」、「微妙な均衡」はともにブッカー賞の最終候補になった。「イギリス人の患者」で知られるマイケル・オンダーチェも、スリランカの白人と現地人の混血で、英語を母語とするバーガーという少数コミュニティーの出身で、スリランカやインドをモチーフにした作品をかなり書いている(最新作「アニルの幽霊」など)。
さらに、世界のボーダーレス化を反映してか、インド人作家がインドと海外に複数の本拠を持って活動する状況が一般的になっていている。若手作家の先陣を切って登場し、「シャドウ・ラインズ」「カルカッタ染色体」など知的な作風で知られるアミターヴ・ゴーシュ、20世紀に残る大長編大河小説「良縁」で文壇の寵児になったヴィクラーム・セート、歴史からゲイ、ITまで多彩なテーマを駆使するヴィクラーム・チャンドラ(「愛と憧れのボンベイ」など)、たゆとうような独特の語り口でベンガルのミドルクラスの日常を描くアミット・チョウドリー(「午後のラーガ」「フリーダム・ソング」など)らは、定期的に欧米で教壇に立つなどインドと海外を行き来している。
日本ではあまり紹介されていないが、欧米の文芸評論では周辺の南アジア諸国の英語作家も、しばしばインド作家の中に含まれることがある(パキスタンのバプシー・シドゥワ、スリランカのロメーシュ・グネセケラ、シャーム・セルヴァドゥライなど)。
また最も広義には、植民地時代にインドで書いていた、あるいはインドを題材にしたイギリス人の作品までもインド英語文学のカテゴリーに入れることがある。
乱暴な言い方をすると、インドがイギリスの植民地になって以降、インドと関わりを持った作家から生まれた文学作品すべてが含まれる。そういう背景であるから、たとえインドで生まれ育ったインド人作家が書いたものであっても、純粋にインドの文学ではなく、イギリスの影響を受け、イギリスあるいは外国の読者の嗜好に迎合した作品である、というマイナスの評価を受け、「欧米人の東洋趣味を煽るだけ」、「まがい物のインドの文学」、さらには「インド文学ではない」と言われてしまうことさえある。
ところが近年流行のポストコロニアル論やカルチュラル・スタディーズでは、このインド英語文学の微妙で複雑な立場こそ、ポストコロニアルの現実の姿そのままであるとして、従来のインドの側からの批判を否定し、積極的に評価する動きがある。アメリカでチットラ・ディヴァカルニーのサイン会に並んでいた移民の二世の少女たちは、インドで「東洋趣味の作り事」と評された本を「自分たちの置かれた現実そのままだ」と言っていた。インドには移民をもはやインド人とはみなしていない人たちもいる。しかし移民とその子孫は異国でインド人意識を保って、二つの社会の中で揺れている。それを彼女の小説が焙り出して見せたのである。
さらに英米では80年代あたりからマイノリティー作家が台頭し、文壇に新しい潮流を生み出し注目されるようになった。「ニューヨーカー」や「グランタ」といった欧米の権威ある文芸誌が他に先駆けてインド系などのマイノリティー作家を紹介した影響も大きいだろう(両誌とも1997年のインド独立50年に際して、インド英語文学の特集号を出している)。インド文学は都会の洗練された読者が、ファッションとして読むようなものにもなったのだ。
こうしてインドでは日陰者だった英語文学が、世界の英文学の中では高い評価を受け、次々と権威ある文学賞を受賞したり、ベストセラーになったりするようになった。イギリスのブッカー賞では90年代を通じほとんど毎年インド、南アジア系作家の作品が最終候補作以上に選ばれている。
話題になっているのは移民作家たちだ、と突き放していたインドでも、アルンダティ・ロイの「小さきものたちの神」が、1997年にインド人として初めてブッカー賞を受賞すると国内の評価は一転した。美女、ITに続き、インド人の英語と文学が世界の一流で通用するという確信を得た(植民地時代の英語を受け継ぐインド人の英語は、語彙が豊富で仰々しいという特徴が指摘されている)。さらに経済発展や核実験の成功に自信を持って、「貧しいインド」から「強いインド」に脱皮したい国内の雰囲気にも合致し、移民作家の作品も含めて「我らの誇り」に奉りあげられるようになった。
新しいインド英語文学の読み方
筆者自身は文学の価値を判断する立場にはないが、新しい英語文学に、これまで知っていた作品では味わえなかったものを感じる、ファン読者を名乗っている。アジア文学に期待されがちな「伝統」や、「草の根の人々の声」といった仰々しいテーマはなく、都市のミドルクラスを描く作品は、どこか乾いてシニカルで、物語も登場人物もいわゆるインドっぽくはない。しかしインドに多少触れた事のある外国人にとっては、農村より都市で我々とあまり変わらない生活をしている人たちの方が現実には触れ合う機会も多いのだ。その彼らが暮らしの中で感じていること、一見アメリカナイズされた生活の中で引きずるインド的な伝統やしがらみが読み取れた時、同じような生活を送る日本の我々と通じる微妙な感性に触れる時、別世界のようなインド文学を読むよりもむしろ響くものが感じられることがある。
若手作家台頭のきっかけになった作品に、ウパマニュ・チャタルジーの「イングリッシュ・オーガスト」がある。主人公の青年アガスティアは都会育ちで、欧米かぶれのタイプと、逆に古めかしい本名をもじって「イングリッシュ・オーガスト」と呼ばれている。最難関の国家公務員試験に合格し、研修生としてヒンディー語も通じない退屈な田舎町に赴任するが、公務員の掟や、ローカルな難題など未知の事態に出くわす。しかし彼は打ちのめされたりも、熱く燃えたりもしない。ボロ官舎の小部屋でひとり悪態をつきながらエクソサイズをし、(人もうらやむ高級官僚の職を)辞める日を思い描くことで、外目には淡々と任務をこなしている。
ヴィクラーム・チャンドラの「赤い大地に降る雨は」では、アメリカ留学帰りの主人公が宗教対立の暴動に出くわす。そこに物言う不思議な猿が現われて、背景にある壮大な歴史を語りはじめる。幕間のように主人公のアメリカでの体験がフラッシュバックし、彼はインドにもアメリカにも居所のない自分に気づき戸惑う。
世界的に話題になったアルンダティ・ロイの「小さきものたちの神」は、旧家の没落の中で成長する双子の姉弟が軸になっている。カースト差別や抑圧される女性、伝統社会の崩壊といったどちらかといえば厳しいテーマが語られているが、子どもの言葉遊びのような文章や、繰り返しあらわれるケララの美しい自然描写からは暗さや深刻さが感じられない。作者もそうした問題を声高に指摘するわけでもない。しかしメッセージはむしろじわじわと沁みてくる。
経済開放や情報革命を謳歌し、インドっぽくない暮らしにシフトしていこうとする今も、若手作家たちは意外にもインドの長い歴史や伝統を強く認識している。特に独立とインド・パキスタンの分離は多くの作者によって作品の中に投影されている。そうした歴史の負債や伝統の重圧に、彼らがどのように対面してるのか、そうした「時の感性」が感じられるだけでも、読む楽しみは尽きないのである。
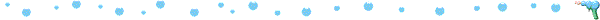
<参考文献>
アッシュクロフト、グリフィス、ティフィン 木村茂雄訳 『ポストコロニアルの文学』 青土社 1998年
関口真理「インド人作家の英文学が面白い」、『ワールトカルチャーガイド9 インド』 トラベルジャーナル 1999年
森本素世子「邦訳で読む南アジア近、現代文学:1990年代の動向から」、『南アジア研究12号』日本南アジア学会 2000年
山本 恒「インドの現代英語小説」
<邦訳のあるインド英語文学>
チットラ・ディヴァカルニー 本名裕子訳 「シスター・オブ・マイ・ハート」DHC 2001年
アユーブ・カーン=ディン 「ぼくの国、パパの国」 白水社 2001年
ジュンパ・ラヒリ 小川義高訳 「停電の夜」 新潮社 2000年
アルダシール・ヴァキル 奥田弥生訳「ビーチボーイ」 花風社 2000年
マイケル・オンダーチェ 畑中佳樹訳 「バディ・ゴールデンを覚えているか」新潮社 2000年
藤本陽子訳 「家族を駆け抜けて」 彩流社 1998年
土屋政雄訳 「イギリス人の患者」 新潮社 1996年
ハニフ・クレイシ 中川五郎訳 「ほくは静かに揺れ動く」 アーチストハウス 2000年
古賀林 幸訳「郊外のブッダ」 中央公論社 1996年
アニタ・デサイ 高橋明訳 「デリーの詩人」 めこん 1999年
岡本浜江訳 「ぼくの村が消える!」 国土社 1984
キラン・デサイ 村松潔訳 「グアヴァ園は大騒ぎ」 新潮社 1999年
インディラ・ガニサン 田栗美奈子 「ソニルの旅立ち」 アーティストハウス 1999年
インド児童文学作家 鈴木千歳編 「トラの歯のネックレス」 ぬぷん児童図書出版 1998年
アルンダティ・ロイ 工藤惺文訳 「小さきものたちの神」 DHC 1998年
片岡夏実訳 「私の愛したインド」 築地書房 2000年
カマラ・ダース 辛島貴子訳 「解放の女神」 平河出版社 1998年
ロヒントン・ミストリー 小川高義訳 「かくも長き旅」 文芸春秋 1996年
小川義高訳 「ボンベイの不思議なアパート」文芸春秋社
バーラティ・ムーカジ 遠藤晶子訳 「ミドルマン」 河出書房新社 1990年
ゴーパール・バラタム 幸節みゆき訳 「いとしい人たち」 段々社 1993年
サルマン・ラシュディ 寺門泰彦訳 「東と西」 平凡社 1997
飯島みどり訳 「ジャガ−の微笑 ニカラグアの旅」 現代企画室 1995
五十嵐一訳 「悪魔の詩 上・下」 プロモ−ションズ・ジャンニ(新泉社) 1990
栗原行雄 「恥」 早川書房 1989
寺門泰彦訳 「真夜中の子供たち 上・下」 早川書房 1989
V.S.ナイポール 武藤友治訳「インド・新しい顔大変革の胎動 上・下」 サイマル出版会 1997
工藤昭雄訳 「終わらなかった旅」晶文社 1991
安引宏訳 「インド・光と風」 人文書院 1985
安引宏訳 「インド・闇の領域」 人文書院 1985
工藤昭雄訳 「イスラム紀行 上・下」 TBSブリタニカ 1983
小野寺健訳 「暗い河」 TBSブリタニカ 1981
工藤昭雄訳 「エバ・ペロンの帰還」 TBSブリタニカ 1982
工藤昭雄訳 「インド―傷ついた文明」 岩波書店 1978
ギータ・メータ 亀井よし子訳 「リバー・スートラ」 講談社 1995年
サラ・スレイリー 大島かおり訳 「肉のない日」みすず書房 1992年
R.K.ナラヤン 森本素世子訳 「ガイド」 日本アジア文学協会 1995
ムクル・ラジ・アーナンド 山際素男訳 「不可触民バクハの一日」 三一書房 1984
R.タゴール『ギタンジャリ』森本達雄訳註 1994第三文明社 レグルス文庫
(作品リストの作者名は本の表記に従った。この他、文芸雑誌、短編集や企画物に収録されているものがある)
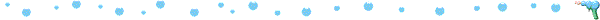
関口のホームページに戻る